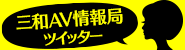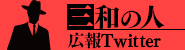憧れの男性の奴隷になった女子大生の告白 ※DVD収録
告白 一条由香(仮名)
私は二十五年以上、貴誌を愛読している者です。初めて投稿させて頂きました。他の皆様のような淫靡な写真ではなく、つたない写真ですが、よろしければ採用のほどお願いいたします。私の奴隷――由香も喜ぶと思います。
手記の方は、由香が自ら書きたいと申し出てきたものです。由香と私が主従となったきっかけには、貴誌の存在がありました。
おじ様の図書室
今、私はこの告白の手紙を、おじ様の書斎で書いています。かつて『おじ様の図書室』と呼んでいた、私がいつも放課後を過ごしていた部屋で、この四年間に思ったことをすべて書こうと思います。
同年代の少年ではなく、大人の男性にあこがれの気持ちを抱いたのは十六歳のときでした。人より早熟だったというわけではありません。尊敬できる魅力的な大人の男性が身近にいたからです。
休み時間、クラスメートがアイドルの話題で盛り上がり、キャーキャーと歓声をあげているときに、私はキスすらしたことのないその人のことを考えては、体を熱くしていました。
中高一貫の女子校ですから、休み時間などはとてもにぎやかです。担任もOGが多いためクラスも家庭的で、クラスメートというより姉妹に近い感じでした。
男性には驚きかも知れませんが、生理用品などもあけすけに貸し借りしますし、誰かが他校の男子生徒に言い寄られたりすると、みんなでこっそりついていって、告白の現場を見守ったりもしました。
男の先生を好きになってしまうのも日常茶飯事です。女子校育ちの私たちは男の子に対して変なプライドがあり、学園祭などでナンパされても簡単には付き合おうとしませんでした。
そのくせ、実は奥手で男の子を誘うことができず、カラオケに行くのもスキーに行くのも女だけです。好きです、付き合ってくださいと告白するとしたら、その相手は誰かのお兄さんか先生でした。
もちろん私も友人たちから、「由香の好きな人、だれ?」「写メ見せてよ」とたびたび聞かれましたが、いつも「今はいない」と言い続けていました。
ついには「由香はビアンだもんね」と言われるようになりましたが(女子校には実際、女どうしで付き合っている人もいました)、それでも好きな人のことは言えませんでした。絶対に誰にも言わないと決めていたからです。
私が好きな人は父の大学時代の親友で、当時すでに四十代の人でした。クラスメートがあこがれている先生や友達のお兄さんというのは、年上と言っても二十代か三十代です。
父親と同い年の男性を好きになる理由を説明しても、わかってもらえるとは思えませんでした。私がその人――田邊さん(仮名)に惹かれてしまったのは、みんなには言えない理由があったからです。
父が「田邊のおじ様を連れて来たよ」と言うと、私も妹も大喜びでした。田邊さんは海外での研究生活が長かったので話がおもしろく、独身で、年よりずっと若く見えました。
私が十六歳のとき、おじ様はアメリカの物理学の研究所から帰国して、うちの近所のマンションで暮らすようになり、ときどき我が家に家庭料理を食べに来ました。
私の学校は中学から高校へはエスカレーター方式で進学できるのですが、英語教育に熱心な大学でした。私も英語が大好きで、英語弁論大会に出たり、部活では英語の絵本を作ったりということをしていました。
学校の図書室には英語の雑誌や新刊本が少ないので、私は田邊のおじ様の家で本を見せてもらうようになりました。おじ様は「由香ちゃんは見どころがある」と言ってくれて、スピーチに使えそうな表現をいっしょに探してくれたりもしました。
おじ様がソファに並んで腰かけ、前髪がふれるくらい近くで本をのぞきこんだりします。おじ様の吸っている海外のタバコの香り、首すじから漂ってくる男の匂い、私はそれが好きで胸いっぱいに吸いこんではクラクラしていました。
心臓のドキドキがおじ様に聞こえたらどうしようと、いつも身を固くしていました。まだ十四歳なのに、四十歳のおじ様が発する大人の男の色気のようなものを感じて、私はおじ様に恋をしていたのです。
家族には「おじ様の図書室に行ってくる」と言って、放課後はまっすぐおじ様の家に向かいます。おじ様は私に合い鍵を渡してくれていたので、宿題もおじ様の書斎やリビングでやっていました。
秘密の書棚
おじ様の書斎とリビングの壁は床から天井まで造りつけの書棚になっていました。ところどころ引き戸が付けてあり、そこにはおじ様の書きかけの論文が突っこんであったり、あまり必要のなくなった古い書籍などが入れてありました。ある日私は宿題に疲れておじ様の書棚探検をしていました。
ふと、いつも開けたことのない高いところにある引き戸に目が行きました。なぜかと言うと、いつもきっちり閉まっている扉が指一本ほど空いていたからです。ソファを踏み台がわりに扉を開けた私はあっと声をあげました。
そこには女性のヌードが表紙になった雑誌や写真集がたくさん入っていたからです。手がふるえました。私だって男性がヌードを見ることぐらいは知っていました。でも、その本に載っている女性のヌードは縛られていたり、首輪をつけられていたり、無残なぐらいにアソコを開かれていたりしたのです。
女性の脚をひろげて棒に縛りつけ、閉じられなくなった股間を複数の男性がのぞきこんでいる写真には、思わず背筋がゾクッとしました。嫌悪感でふるえたのだと思いましたが、それなのに目をそらすことができませんでした。
女の人はみんな恥ずかしそうで、泣きそうで、でもうっとりと陶酔しているようにも見えたのです。体の奥までカーッと熱くなっていました。置き場所をまちがえないように気をつけながら、一冊ずつ見入っていきました。
それがSMと呼ばれる世界だいうことは知りませんでした。ただ、おじ様がこんな本を隠し持っていることは父もきっと知らないし、知られてはならないことだ、と直感しました。そして、大好きなおじ様の秘密を自分だけが知っていると思うと、叫び出したいほどの喜びでいっぱいになりました。
おじ様に対する私の恋心は一生片思いで終わるはずでした。しかし、おじ様が結婚しない理由はこの嗜好のせいにちがいない、と気づいてしまった私は、この本の女性たちの代わりに私がおじ様の愛欲をかきたてたいと願うようになったのです。
この続きは、マニア倶楽部2020年1月号をご覧ください。