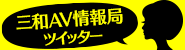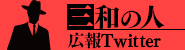兄嫁の箱入り妻を奴隷にした男性の告白
告白 栗林(仮名)
眩しすぎた笑顔
うそのような幸運が重なって今現在、私はとある、いまどき珍しいぐらい清楚な人妻の尻の穴を調教し、弄び、味わい尽くしています。
そしてその清楚な人妻というのは他ならぬ私の義理の姉、実の兄の妻なのです。言うまでもないことですが、口が裂けても兄には言えない関係です。
私の肛門奴隷、義姉のさとみは、本当にお嬢様育ちで、純真で、貞淑で、まともな羞恥心を持ち合わせた人間です。こんな女を調教できる機会はもう二度とないでしょう。
さとみをとことんまで、堕ちるところまで堕としてやるのが、この偶然の機会を得た自分の使命だとさえ、私は思っています。
ですから義姉さとみのさらなる転落の序章として痴態をカメラで撮影し、全国のマニアの皆様にご覧いただこうと思い、この投稿に至りました。
非道徳で強引な部分もありますが、ここに至った経緯を書かせて頂きます。今となってはさとみは私の調教無しで生きていけない体ですし、本人もこの快楽を知ることができて、よかったと言っています。どうかさとみの渾身の痴態を、彼女のためにも見てやってください。
思えば私はさとみのことを、兄が初めて家に連れてきたときから狙っていました。
さとみは、兄よりも十五歳も年下の、当時二十代の若い女性でした。弟の私と比べても十歳も離れているのです。
そのプロフィールをここに詳しく書くわけにはいきませんが、実家は四代以上続く資産家のご令嬢で、親族には叙勲者もいるという非の打ち所のない家柄の出でした。さとみ本人も、地元で有名な中高大まで一貫のお嬢様学校を卒業した、正真正銘のお嬢様だったのです。
兄とは、仕事上の付き合いで出会ったとのことでした。
「初めまして、どうぞよろしくお願い申し上げます」
弟の私にまで深々と頭を下げ初対面の挨拶するさとみは清潔感があり、育ちの良さがにじみ出ていました。挫折も劣等感もない人生を歩んできた人間の素直さを感じました。
その嫌味のない笑顔は、私にとって眩しすぎたのです。
その笑顔を見た瞬間から私は、どうしてもこの女が堕ちる姿を見てみたい、自分だけの奴隷にしたいという、どす黒い感情を抑えられなくなったのです。
そして、さとみを奴隷にする絶好の機会が、ついに訪れたのです。今から2年前、さとみが三十歳になってすぐというタイミングでした。
捕食者の愉悦
兄が家をリフォームすることになり、そのために2カ月ほど実家で兄とさとみの夫婦が暮らすことになったのです。
兄の家にある荷物も運び込んだので、ちょっとした引っ越しの様相でした。その搬入は私も手伝ったので、その際に「何か面白いものは無いか」といろいろ物色してみたのです。
荷物の中に、妙に大事そうにしまわれている荷物がありました。丁寧なガムテープの貼り方が、兄の作業ではないということを物語っています。
これは、さとみの荷物に違いない。私はそう確信しました。
そして、家族の全員が不在になったタイミングを見計らって荷物の中を覗いたのです。
荷物の中身の大半は可愛らしい思い出の品でした。でもその中に、鍵のかかった綺麗な箱を私は見つけたのです。
普通なら、鍵は別の場所に保管しそうなものですが、引っ越しの荷物ということで、ご丁寧に同じ段ボールの中にあったのです。私はもちろんそれを開けて中を見ました。
箱の中は手紙でした。さとみの高校時代の、ラブレターとおぼしきものでした。
微笑ましいというか、時代錯誤というか。さとみの年代ならすでに携帯のメールが普通だったろうに。そう思いながら手紙を眺めているうちに、私はとんでもないことに気づきました。
さとみの相手は、何とその高校の教師だったのです。
相手からの手紙しかないので詳細はわかりませんでしたが、さとみとその教師がかなり親密だということはわかりました。
「驚かせるようなことをしてごめんなさい。でも、受け入れてくれて本当に嬉しかった」
「体中、どこもかしこも可愛かった。時間を気にせず、もっといっぱい愛してあげたい」
そんな歯の浮くようなセリフがいくつもいくつも書かれていました。それを読み込んでいくうちに、さらに驚愕の事実が明らかになったのです。
手紙を書いている教師は、男ではなく、女の教師でした。
さとみは、学生時代、学校の女教師と肉体関係を持っていたのです。
「これは使える……」
思わず独り言が漏れました。
私は箱ごと拝借し、すべての手紙をスマホで撮影しました。
兄の家のリフォームが終わり、さとみたちが家を出ました。
私は、家族が家にいないタイミングを見計らって、さとみに連絡を入れました。
「たぶん、さとみさんの忘れ物だと思うんですけど、鍵付きの箱があって……」
さとみは電話口で絶句していました。さとみはすぐ、私の家にやって来た。その顔には狼狽の色がありありと浮かんでいて、すでに憔悴してさえいました。
「あの……忘れ物を、取りにきました……」
さとみの声はかすれていました。整った顔から、あの眩しい笑顔も消えていました。
「何かわからなかったので、中身を確認してしまいました」
私が言うと、さとみは震え出しました。その狼狽ぶりは見ているのが気の毒なほどです。
この程度の、十年以上も前の出来事など、普通の人間にとってはちょっとした火遊びみたいなものでしょう。しかしさとみは、この事態をかなり重く深刻に捉えているようでした。
きっと彼女にとっては誰にも話せない、墓場まで持っていく秘密だったのでしょう。
私にとって、好都合でした。
「知ってしまった以上、見過ごせません。兄に伝える前にまずはきちんと説明してください」
兄の名前を出すと、さとみはさらに狼狽し始めました。
その手紙はただの意味のない悪ふざけで、事実ではないのでどうか忘れて欲しい、そう私に懇願してきました。
「体中、どこもかしこも可愛かった。時間を気にせず、もっといっぱい愛してあげたい」
私が無表情のまま手紙の内容を口に出すと、さとみは唇を震わせながら絶句しました。
「こんなセリフを教師が生徒に書くことがただの悪ふざけだなんて。そんなごまかしは通じません。正直に話してください」
さとみは観念して、すべてを白状しました。高校時代に出会ったその女教師とはかなり親密な仲で、レズセックスまでしていたそうです。私は呆れたような表情を浮かべ、言いました。
「……義姉さん。僕は兄さんの奥さんがレズだと知って、それを黙っていることにはかなり抵抗があります」
そのときのさとみのうろたえぶりは見ものでした。あの挫折知らずのお嬢様が、目も当てられないほど取り乱したのです。
「違います、違います、そんな経験はその先生だけ……たったひとりだけなんです!」
私は訊き返しました。
「では、男性は?」
「○○さん(兄)だけです……」
さとみは、答える義務のないことまで口走りました。それほど錯乱していたのでしょう。
「わかりました。ちょっと僕に考えさせてください」
私は椅子から立ち上がりました。今日のところはここまでで十分だと思ったのです。
「いまの会話は、僕のスマホのボイスレコーダーですべて録音させてもらいました」
整ったさとみの顔が歪みました。絶望を絵に描いたような顔というものがあれば、そのときのさとみの顔がそれでした。
「また連絡します。人のいない場所でお話ししましょう」
さとみが私の連絡を無視することは、もうできません。私は自分の計画が順調に滑り出していることを感じました。
この続きは、マニア倶楽部2024年11月号をご覧ください。