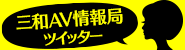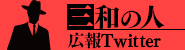マゾ性癖を捨てられなかった看護師の告白 ※DVD収録
告白 ミミコ(PN)
病院と、痴漢と
私という女は、いつからこんなに歪んでしまったのでしょうか。ときどきそう思うのです。
ふつうになりたい、まともになりたいとずっと思い続けているのに、どうしても異常な性行為に惹かれてしまうのです。
逃れられないのでしょうか、それとも自分から地獄に堕ちているのでしょうか。それが自分でもわからないのです。
私にはご主人様がいます。そして今、その方からひどい仕打ちを受けようとしています。
逃げようと思えばできるのかもしれません。でも私はそうしないのです。それは私が真性のマゾヒストだからです。
私がマゾになったのは、一体いつからなのでしょう。
子供時代の私は病弱で、物心ついた頃から病院通いの毎日を送っていました。子供は病院が嫌いと相場が決まっていますが、私は違いました。
お医者さんに服を脱がされて体に触れられることが、何ともいえず気持ちよかったのです。
ピカピカ光る医療器具や薬品の匂いも私にとっては心地よいものでした。あんな器具や薬の実験台に自分がなることを妄想し、人知れず興奮しているような変な子どもだったのです。
そして、中学時代に決定的な出来事が起こりました。
電車通学だった私は、痴漢のターゲットにされたのです。
この頃にはもう私は病気がちではありませんでしたが、病院通いの影響なのか、内向的でうつむきがちな子に育っていました。そんな大人しい私はきっと痴漢から格好の獲物に見えたのではないかと思います。
同じ人が、毎朝同じ車両で私の制服のスカートの中に手を忍び込ませてきました。
もちろん初めはショックでしたが、私は車両を変えることもせず、毎朝黙って自分の肉体をその痴漢に差し出したのです。
自分でも理由はわかりません。ただこんな理不尽な行為に胸が高鳴って、性的なドキドキを得ていたのは事実です。
その痴漢の男性も、飽くことなく私を触り続けました。その指先の感触を、私はいまでも思い出すことができます。
パンティの上からお尻をたっぷり、熱く火照るほど撫でまわした後、手を前に回して下着の中に指を忍ばせるのです。
周囲には大勢の人がいるのに誰にも気づかれないまま、自分の体が慰みモノになる。それがたまらなく背徳的で、私の幼い性器は蜜を溢れさせました。
事後に駅のトイレで着替えるために、替えのパンティを持参するほどだったのです。
やはりこれは、病院通いをしていた幼少時に、他人の手で肌に触れられる快感を知ってしまったからかも知れません。
そして夜になると、医療器具を使ってその痴漢の男性に犯される妄想でオナニーしました。
私の破瓜は、男性との性行為ではありません。両親に内緒で手に入れた医療用のクスコ(膣鏡)を使ってオナニーしていて、気がついたら出血していたのです。高校一年生の秋でした。
薬剤師の変態調教
そんな「医療フェチ」だった私は、学生時代のバイト先にも薬局を選んだのでした。
そしてその薬局にいた薬剤師の男性こそ、後のご主人様になる男性でした。
「仕事の後、時間ある?」
そう話しかけられた私は内心「またか」という感じでした。
無口で無抵抗なタイプに見える私は学生時代から御しやすいと思われるのか、男性から誘いを受けることが意外なほど多かったのです。
ですが私を満たす男性はいませんでした。
ベッドに入るとかそんなことではありません。それ以前の会話だけで醒めてしまうのです。
私の中の暗い内面を見抜いた男性が、いなかったのです。
ですから私はこのときも、社交辞令のつもりで、男性と飲みに行きました。でもそれは、私の誤算だったのです。
「××さんはマゾヒストだね」
「えっ、なっ」
「それも強い嗜虐性をもっている。ハードマゾ」
注文したアルコールがテーブルに運ばれると、彼はそう切り出しました。
私は自分がそんな素振りを見せたことがあっただろうか? と不安な気持ちになりました。
「決めつけないでください」
男性の一方的な話し方に、私も反論します。
「でも、ボロボロにされたいのは本当だろう?」
「……そんな事はありません!」
「××さんは気づいて無いかも知れないけれど、時々、見えるんだよね」
「……」
「自身のなさから来る優柔不断なところとか……」
私はゴクッと唾を飲み込みました。
「この前も、××さんは全く悪くないのに、Aさんに強く言われて、すぐ謝罪していたよね」
「……」
「ほら、今も僕に断定されると」
突然、手首を捕まれました。強く握られました。捕まれた手首が熱くねつをもって、ジンジンと痺れてきました。
「イヤなら」
彼が私を見つめています。私は眼を反らしたいのに、なぜかそらせません。
「手をふりほどいてごらん」
囁くように耳元でそう言われ、私の心臓は早鐘のように鼓動を打ち始めました。
この続きは、マニア倶楽部2021年9月号をご覧ください。