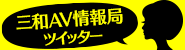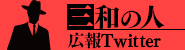セレブ妻を奉仕奴隷にした男性の告白 ※DVD収録
告白◎大野康治(仮名)
奴隷の条件
私は、欲望に打ちひしがれる女が好きだ。貞淑を装い、社会正義を貫き、それでも奥底にくすぶる欲望の火種に身を焦がしし、男に屈服する女を見ていると、得も言われぬ充足感を覚える。それは単なるセックスで得られるものではない。私がSMの世界に足を踏み入れたのは、必然だったのだと思う。
だからといって、SMクラブという選択肢は私にはない。経験したことがないわけではないが、仮初の主従関係に興味を惹かれないし、彼女たちの多くは自らのマゾヒズムを自覚し、それを受け入れている。彼女たちには、欲望はあっても逡巡がない。遅疑がない。葛藤がない。世の変態紳士たちにとっては喜ばしいことかもしれないが、私は少々物足りなく感じる。
それゆえ、私は奴隷に器量を求めない。憐憫を強く感じさせる女であることが奴隷の条件なのだ。その点、芙美子は私にとって理想の奴隷である。彼女は、公務員の夫を持ち、高校生の息子と中学生の娘と、東京西部の閑静な住宅街に暮らしている。実家は大地主の資産家で、不動産収入もあり、生活には何ひとつ不自由がない。逢瀬の際に利用する宿泊料金や食事代、タクシー代もすべて芙美子が支払っている。何も私が命じているわけではなく、何とはなしに自然とそのような流れになった。月に二回程度ではあるが、それなりの金額にはなる。専業主婦という身でありながら、夫に知られることなく、工面できるのだから、その蓄えは相当なものがあるだろう。私もそれなりの収入を得てはいるが、総資産でいえば、芙美子の足元に及ばないと思う。
写真をご覧いただければわかるように、ルックスもスタイルも年相応の平凡な女だ。これまでの経験人数も夫を含めて、わずか三人。私に出会うまではオナニーすらしたことがなかった。話を聞いていると、興味はあったそうだが、怖くてできなかったようだ。四十二歳にもなって、そんな話もろくにできない、絵に描いたような奥手である。私と出会わなければ、そのまま何も知らず、平穏に死んでいく運命にあったはずだ。
だが、芙美子は道を踏み外し、今では私に逢わずにはいられない。見下され、蔑まれ、苦しみを与えてくれる私だけが自分を解放してくる唯一無二の存在だと信じている。無論、私も彼女の信頼に応えていくつもりだ。なぜなら、このような女こそ、私の奴隷にふさわしいからである。芙美子は、もう私の運命の輪の中にいるのだ。
生と性の解放者
芙美子との出会いは、今から二年前、ある懇親会でのことだった。詳しくは書けないが、彼女は私のビジネスに興味を抱き、顧客になりそうだった。四十歳になったのを機に、彼女自身も何かを変えたいと考えていたらしい。
芙美子は、飾りっ気のない濃紺のドレスに白いロングスカーフ、ラウンドトゥのローヒールという地味な出立だったが、年甲斐もなく、肌を露出したキラキラのドレスに身を包んだ年増女よりも、よほど品があり、私はひと目で芙美子のことが気に入った。途中、言葉を切らしてしまうほど緊張している様子で、目が合うとすぐに顔を伏せてしまう。少し垂れ下がった頬にはうっすらと赤く染まっていた。芙美子の話し下手は今でも変わらない。
「ごめんなさい。昔から話すのは苦手で……」
そう言って、苦笑いを浮かべながら髪を耳にかける仕草に、得も言われぬ劣情を駆られ、私は彼女の奴隷姿を思い描いた。何の変哲もないこの女が、私に跪き、犬のように調教される。私のサディズムは、にわかに沸き立っていた。
私は名刺を渡すと同時に、LINEの交換を促した。芙美子は逡巡した。見知らぬ男とアドレスを交換した経験などなかったからだ。だが、裏を返せば、彼女も後ろめたい気持ちを抱いているからこそ、躊躇ったのだ。私は、芙美子の柔らかな頬が強張るのを見逃さなかった。それは不安と期待の表れだ。芙美子を奴隷にする可能性はゼロではない。そう悟ったのだった。
「お仕事の相談だけですから。LINEは一般的に仕事でも使用されています。プライベートなご連絡は一切いたしません」
芙美子は、その言葉に安心したようだった。表情の緊張は解け、先ほどよりも緩んだ笑顔を見せた。緊張と緩和。わずか十五分ほどの会話で、彼女は何度も表情を変えた。私は確信した。芙美子自身にも、奴隷としての才能があると。
SMとは、緊張と緩和の連続だと私は考えている。時に厳しく、時に甘やかし、そうして徐々にマゾヒズムを馴致させていくのである。その過程にこそ、私が考えるマゾヒズムの美しさがある。理性の層を外側から破壊するのではなく、奴隷が内側から突き破る。私のサディズムの本質はその手助けにある。そもそも理性は、本能を抑圧するためのだけのものではない。本能を調整する弁のようなものだ。それが良識やマナー、コンプライアンスなど、外部からの抑圧が弁としての機能を奪い、本能から光を奪った。誰に他人の性を罵しり、侮蔑する権利があるのだろうか。私にとって、社会正義と呼ばれるようなもののすべては、人間から性だけでなく、生を奪っているように見える。人間らしい生に、性は欠かせないはずだ。いわば私は自分を、生の解放者だと考えている。おこがましいかもしれないが、それが私のサディズムだ。
私の目には、芙美子の生は暗い地底に沈んでいるように見えた。だからこそ、私は芙美子を奴隷にしようと決心したのだ。
この続きは、マニア倶楽部2021年1月号をご覧ください。