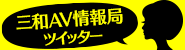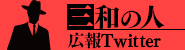緊縛調教に憧れつづけた令嬢の告白 ※DVD収録
告白 小春(PN)
私は今、ある男性に調教していただいています。私のご主人様は調教日記をつけていて、そのノートには私が過去にした話などがきれいに整理されて記されています。撮影した調教写真もきれいに切り貼りされていて、普通の大学ノートのはずなのに、ページをめくるとまるで本物の雑誌のようです。ご主人様はときどき私にそれを読ませてくださいます。
ご主人様が言うには、このノートは「私の成長記録」だそうです。各項目ごとに、ご主人様の感想を書き込む欄があり、私はいつもそこに釘付けになります。
たとえば、初めて調教していただいた日のこと。私はご主人様の命令のままに、緊縛オナニーをすると、何度もイってしまい、ご主人様に「まだイってはダメだと言っているのがわからないのか!」と叱られ続けて泣きじゃくってしまいました。お尻を何度もぶたれて、私は悲しい気持ちが止まらなくなりました。お尻の痛みで泣いていたわけではありません。いつまで経ってもご主人様の言う通りにできない自分が情けなくて、期待に添うことができない自分に耐えられなかったのです。
「本当にお前は悪い子だな!」
ふだんは温厚で物静かにお話してくれるご主人様ですが、イクのを我慢することさえできない不出来な私を躾けるために、人が変わったように荒々しく、調教してくださいます。
成長日記には、その時のご主人様の感想が書いてありました。
「小春のオマンコはおねだりばかりで、まだ聞き分けができないようだ。大人のオマンコにするためには、私が育て直さないといけないのだろう。それに加えて、おぞましさを覚えるほどにイキやすい。どうも羞恥心が向社会的行動に結びつかない。何かが欠落している。やはり幼少期の体験が根深いようである」
私は、思います。きっとご主人様は私を本当に深い愛情で育て直してくださっているのだと。だから、ご主人様の愛情に応えられるように、私はもっとがんばらなくちゃいけません。日々そう思っていますが、どうしても縄で縛られると、私のオマンコはおかしくなってしまうのです。
ご主人様のノートにあるように子どもの頃の出来事が影響しているように、私自身でも自覚はしているつもりです。そこで、ご主人様に「一度自分の言葉で文章にしてみないか」と勧められ、今回、筆をとることにしました。
恐ろしい童話
私がこんなにも緊縛オナニーに染められてしまった原因は、幼稚園の頃に見たおじい様の秘蔵写真のせいだと思います。
私の家は、貿易商を営んでいた祖父を頂点にした厳格な家でした。私が生まれたときには、お父様は婿養子で、祖父の稼業を継ぐために世界中を飛び回り、お母様もまた翻訳の仕事をしていたので、両親ともにあまりに家にいませんでした。そんな私の世話をよく見てくれたのが、おばあ様でした。私が子どもの頃の、おばあ様は60代でしたが、ふだんから色とりどりの和服を身につけ、その所作も佇まいも気品にあふれていました。それに加えて、文筆を趣味としていて、知性も知識も豊富でした。私がよく小説を読むのも、おばあ様の影響が強いからだと思います。
おばあ様はいろんなお話を聞かせてくれました。そのなかでひとつだけとても恐ろしい童話があって、今でも強く印象に残っています。それが「うりこひめとあまのじゃく」というお話です。私は大学で民俗学を専攻し、このお話をテーマにして卒業論文も書きました。
うりこひめは漢字で書くと、「瓜子姫」と書きます。このお話は地方によって、お話の展開がさまざまですが、おおまかなあらすじだけを説明すると(すべて書いていると日が暮れてしまうので)、大きな瓜のなかから生まれた瓜子姫は、老夫婦に育てられますが、留守番をしている最中に「絶対に誰も家にいれてはいけない」と言われていたにもかかわらず、天邪鬼にそそのかれ、天邪鬼に殺されてしまうのです。瓜子姫が生きているパターンの話もあるのですが、おばあ様の地方で伝わっている話では、天邪鬼が瓜子姫の皮をはぎ、その皮を着て瓜子姫に化けた天邪鬼が、瓜子姫の死体を老夫婦に食べさせてしまうというおぞましいものでした。
私が初めてこの話を聞かれたとき、あまりの恐ろしさに涙が止まりませんでした。おばあ様は、泣きじゃくる私をそっと抱き上げて、その温かい両手で包み込むと、やさしく問いかけました。
「ごめんなさいね、とても恐ろしかったでしょう? でもね、この世界には絶対に開けてはいけない扉があるのよ。だから、おじい様やおばあ様とお約束したことは絶対に守ってちょうだいね。おばあ様は小春ちゃんに瓜子姫にはなってほしくないもの。小春ちゃんはいい子だからお約束できるわよね?」
私はしゃっくりが止まらないせいで、ろくに言葉を発することもできませんでしたが、首を縦に振って、おばあ様と約束しました。あの出来事はまだ3歳か4歳ごろでしたが、今でもはっきり思い出せるほど、私にとって忘れられない経験となりました。
この続きは、マニア倶楽部2019年1月号をご覧ください。